【鵜戸神宮 概要】
鵜戸神宮(うどじんぐう)は正確な創建は不明。古代以来の海洋信仰の聖地とされ本殿の鎮座する岩窟は豊玉姫が主祭神を産むための産屋を建てた場所されいます。諸説あるようですが崇神天皇(第10代天皇)の時代に創建されたと伝えられており、その場合、紀元前148年~紀元前30年となります。記録上では桓武天皇(第50代天皇)の延暦元年(782年)、天台宗の僧侶光喜坊快久が勅命によって神殿を再興したそうです。

平安時代以来、海中に聳える奇岩怪礁とも相俟って、修験道の一大道場として「西の高野」とも呼ばれる両部神道の霊地として栄えましたが、明治の神仏判然令により現在の形になりました。
御祭神は、日子波瀲武鸕鷀草葺不合尊(ひこなぎさたけうがやふきあえずのみこと)「豊玉姫の子であり神武天皇の父」、大日孁貴(おおひるめのむち)(天照大御神)、天忍穂耳尊(あめのおしほみみのみこと)、彦火瓊々杵尊(ひこほのににぎのみこと)、彦火々出見尊(ひこほほでみのみこと)、神日本磐余彦尊(かむやまといわれひこのみこと)(神武天皇)を祀っております。
【鵜戸神宮 神門】

二の鳥居を潜ると見えてくるのが最初の門である神門。奥にある楼門より小振りですが、何とも風格があります。

参道からは太平洋を一望でき、荒波が打ち寄せる絶景が楽しめます。
【鵜戸神宮 楼門】

神門の先には、見事な楼門(ろうもん)があります。こちらはとても迫力がありました。
【鵜戸神宮 玉橋】

この橋から本殿がある洞窟へ降りていきます。ここらの景色が鵜戸神宮として有名ではないでしょうか。

【鵜戸神宮 亀石と運玉】
本殿前にある霊石で、豊玉姫が海神宮(わたつみのみや)から来訪する際に乗った亀が石と化したものと伝わっています。

運玉を投げて亀石の背に四角い窪みがあり、そこに運玉が入ると願い事が叶うという言い伝えあり、運試しをするのが名物となっています。作法としては男性は左手、女性は右手で投げるそうです。 多くの訪問者が楽しんでおり時折歓声が上がっていました。
【鵜戸神宮 本殿】
洞窟の中に本殿があり、神秘的な雰囲気を醸し出しています。

潮風が吹く場所の為か、これまで何度も改修を得ており、1997年(平成9年)にも改修が行われています。しかし、その様式は往時のままであり現在は県の有形文化財に指定されています。
【鵜戸神宮 お乳岩( おちちいわ )】
本殿の奥をぐるりと回ると奥に乳岩があり、これが謂れで安産、子宝、子の成長にご利益があると考えられていると思われます。

神話では豊玉姫が出産後、綿津見国へ帰る前に、乳房を切り岩に移し、そこから出る「お乳水」で主祭神が育ったとされています。
【鵜戸神宮 近くにある観光スポット】
青島神社
【鵜戸神宮 アクセス】
管理人の感想
厳しい崖の中腹に本堂がある珍しい神社です。現在は比較的に簡単に来れますが、江戸時代までは修験者の一大道場であったようです。海岸の岩もダイナミックな造形で景色としても素晴らしい場所です。
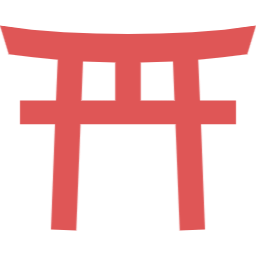 日本の絶景神社仏閣 参拝記
日本の絶景神社仏閣 参拝記 






