【築土神社 概要】
築土神社(つくどじんじゃ)は940年(天慶3年)に創建。平将門の首を祀るために、江戸の津久戸村(現在の将門塚付近)に「津久戸明神」として建立されたのが始まり。その後、何度か移転や改称を繰り返し現在の場所に鎮座しています。1945年の東京大空襲によって平将門の首(頭蓋骨や髪の毛)を納めたという首桶や肖像画などが全焼しています。昔は「田安明神」とも呼ばれ、日枝神社、神田明神とともに江戸三社の一つに数えられていたそうです。
現在は天津彦火邇々杵尊(あまつひこほのににぎのみこと)を主祭神とし、平将門、菅原道真を祀っています。平将門は武道の神様として知られており、日本武道館の氏神でもあります。
【将門の首塚】

平 将門は怨霊としての伝説も語り継がれており崇徳天皇や菅原道真と並んで「日本三大怨霊」の一人とされています。その祟りは現代でも恐れられており、将門の首塚は、移転することができません。過去に移転を試みた際に様々な怪奇現象や不幸が起こったという伝承があるためです。戦後のGHQによる開発の際に、移転を試みたところ関係者が不審死・重機が横転するなどの事故が相次ぎました。現在も東京大手町の超一等地の高層ビルの間に墓石があります。
【将門塚 アクセス】
【築土神社 境内】
都心の神社なのでビルの谷間にあり、知らないと気づかないで通り過ぎてしまうかも知れません。

【築土神社 社殿】
ビルの敷地内という立地なせいか近代的な印象を受けます。この社殿は1994年(平成6年)、境内にオフィスビルを建設するとともに、鉄筋コンクリート造として新築しています。

ビルの1階に鎮座し、独特の雰囲気がありますが、社殿はしっかりした作り。
【築土神社 境内 世継稲荷】

二代将軍徳川秀忠が田安稲荷と称されていた社を参内し「代々世を継ぎ栄える宮」と称賛された事による謂れから『世継稲荷』と称されるようになった社が築土神社の社務所手前の左側に鎮座しています。

【築土神社 近くにある観光スポット】
靖國神社、日本武道館、皇居、東京大神宮
【築土神社 アクセス】
管理人の感想
当時の日本政府やGHQがお手上げの将門の首塚は有名なお話。平将門と聞くと怖いイメージがあり西(京都)では極悪人扱い。しかし、東(関東地方)では荒れ地を農民と一緒に開墾し圧政から立ち上がった英雄であり、関東で語り継がれている場所も多いです。過去の偉人に経緯を払う意味でも付近にある靖国神社と合わせて参拝されてはいかがでしょうか。
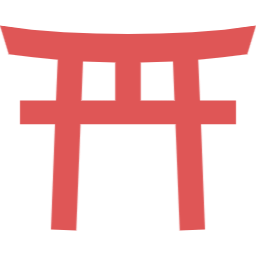 【御朱印・絶景】日本の神社仏閣めぐり – JAPAN SHRINE GUIDE
【御朱印・絶景】日本の神社仏閣めぐり – JAPAN SHRINE GUIDE 

















